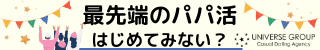このページは、「乱視の見え方・症状・原因から検査・治療方法・予防対策まで徹底解説!」について、わかりやすく解説していきますので、参考にしてもらうためにお伝えしていきます。
このページは、「乱視の見え方・症状・原因から検査・治療方法・予防対策まで徹底解説!」について、わかりやすく解説していきますので、参考にしてもらうためにお伝えしていきます。
モノが二重や三重に見えたり、夜にモノが見えにくくなる乱視は、角膜や水晶体の歪みによって引き起こります。
乱視は、角膜や水晶体の歪みによって、モノの焦点が合いにくくなり、モノが見えづらい症状が現れます。
乱視の治療は、主にメガネやコンタクトレンズによる矯正が行われて、強い乱視の場合にはハードコンタクトレンズが使用されます。
では、「乱視の見え方・症状・原因から検査・治療方法・予防対策まで徹底解説!」について詳しく解説していきます。
1.そもそも乱視とは?
乱視とは、角膜や水晶体が歪んでしまっているので、焦点が合わずモノが二重に見えたり、モノがぼやけて見えるといった症状が目に現れることを指します。
乱視には、実は「正乱視」と「不正乱視」の2種類があります。
(1)正乱視
(2)不正乱視
(1)正乱視
乱視には、正乱視と不正乱視があり、角膜や水晶体がキレイな楕円ではなくて楕円形に歪んでいることで、目から入ってきた光の焦点が2箇所にできてしまう乱視のことを正乱視といいます。
一般的に乱視といえば、正乱視のことを指します。
正乱視の中でも3種類があり、レンズが縦方向に歪んでいるものを直乱視、横方向に歪んでいるものを倒乱視、斜め方向に歪んでいるものを斜乱視といいます
【直乱視】上下方向に潰れるように歪んで見える
【倒乱視】横方向に潰れるように歪んで見える
【斜乱視】斜め方向に潰れるように歪んで見える
正乱視のほとんどの場合は、直乱視です。
(2)不正乱視
不正乱視は、角膜の表面がデコボコなっていることで起こる乱視です。
正乱視は、2点で焦点が結ばれていますが、不正乱視の場合はどこにも焦点が結ばれていません。
不正乱視は、円錐角膜や角膜潰瘍、外傷といった角膜の疾患やレーシックなどの屈折矯正手術の後遺症として、後天的に起こることがある乱視です。
2.乱視の見え方や症状とは?
乱視の場合は、目から入ってくる光の焦点が2箇所出来てしまうことで、以下ようなモノの見え方をする症状が現れます。
・モノが二重に見える
・モノが三重に見える
・縦や横にモノがだぶるようにブレて見える
・近くや遠くのモノがぼやけて見える
・光が滲んで見えたる
本来であれば、目から入ってきた光は、角膜や網膜の屈折力によって網膜の一点にピントが合うのですが、角膜や水晶体が歪んでしまっている乱視の場合は、焦点が2点出来てしまったり、そもそも焦点が結ばれていないことになるので、モノが二重に見えるや三重に見えるなどの症状が現れてきます。
また、乱視の症状は、夜にモノが見えづらい、夜間の車のヘッドライトがぼやけて見えるなどの目の見え方に関する症状以外にも頭痛や眼痛を伴うことがあります。
乱視は、モノがぼやけて見えてしまっている状態なので、モノが見えにくい状態を改善するためには、目の筋肉が絶えずピントを合わせようと動くために、目に疲労が溜まりやすくなり、頭痛や眼痛といった眼精疲労の症状が現れやすくなります。
3.乱視の原因
乱視の原因は、角膜や水晶体の歪みです。
角膜や水晶体は、目から入ってくる光を屈折させて、目の眼底(目の奥)にある網膜に焦点を結ぶ役割を果たしています。
屈折力によって、網膜に焦点が結ばれることで、モノをはっきり見ることができます。
しかし、角膜や水晶体の歪みによって、焦点が合わない乱視の場合には、モノがはっきり見えない症状が現れてきます。
ただし、乱視は何も特別なものではありません。
私たちの目には、個体差がありますので、誰でもある程度の乱視状態といえます。
角膜や水晶体は、完璧な球体ではなくて、ある程度は歪んでいます。
そのため、程度の差こそあれど誰でも乱視の状態といえます。
軽微な角膜や水晶体の歪みの場合には、視覚にそれほど影響が現れませんので、一般的にいわれるような乱視の症状が現れることはありません。
しかし、角膜や水晶体の歪みの度合いが大きい場合には、視覚に与える影響が大きくなりますので、個体差による歪みの大きさからモノが二重に見えたり、モノがぼやけて見えたりする乱視となってしまいます。
また、一般的に乱視といえば、角膜や水晶体の歪みによる正乱視のことを指しますが、角膜の疾患や矯正手術の後遺症として後天的に発症する不正乱視もあります。
不正乱視は、角膜の表面がデコボコになっていることが原因です。
4.乱視の検査方法
乱視の検査は、主に放射状の線からなる乱視表を使って行われます。
乱視の検査のことを乱視表「乱射線乱視表測定」といいます。
乱視の場合には、ピントが合っていない方向の線がはっきり見えますが、ピントが合っていない方向の線はぼやけて見えてしまいます。
「ピントが合うか?合わないか?」は、「線がぼやけるか?ぼやけないか?」とは逆の関係になりますので、ピントが合わない方向の線がはっきり見えて、逆にピントが合う方向の線がぼやけて見える形になります。
乱視の乱視表(乱射線乱視表測定)は、インターネットで検索すれば、すぐに見つけることができます。
乱視が気になっている方は、一度乱視表(乱射線乱視表測定)で確認して見ると良いでしょう。
5.乱視の治療方法
乱視の治療方法は、基本的にメガネやコンタクトレンズによる矯正が行われます。
乱視の程度が弱い場合には、円柱レンズであるメガネやソフトコンタクトレンズによって、矯正することができます。
乱視の度合いが強い場合には、メガネやソフトコンタクトレンズでは限界があるので、ハードコンタクトレンズによる矯正が行われます。
しかし、最近は、以前ではハードコンタクトレンズでしか矯正できなかった乱視の場合であってもソフトコンタクトレンズによって矯正できるようになっています。
以前では、ソフトコンタクトレンズの場合は、角膜の歪みに沿ってコンタクトレンズを柔らかく歪んでしまうため、矯正することが難しかったのですが、最近の医療技術の発展によって、新しいソフトコンタクトレンズが発売されるようになって、ハードコンタクトレンズでしか矯正できなかった乱視も新しいソフトコンタクトレンズで矯正できるようになりました。
ただし、新しいソフトコンタクトレンズであっても、上手く矯正できない場合もあります。
乱視を本格的に治療したいと考えている方には、レーシック手術やオルソケラトロジーなど選択肢があります。
(1)レーシック手術
(2)オルソケラトロジー
(1)レーシック手術
正乱視は、通常のレーシックで矯正することができます。
しかし、不正乱視の場合は、ウェーブフロントレーシックという、角膜の歪みを正確に捉えてくれるレーシックでのみ治療が可能です。
・一度の手術で効果が持続できる。
・コンタクトレンズのように維持費がかからない。
・裸眼で過ごせるようになる。
・強度乱視の場合は、軽度な乱視が残る可能性がある。
・適応検査で不適応になるとレーシック手術を受けることができない。
・ドライアイやハログレアなどの後遺症が現れる可能性がある。
(2)オルソケラトロジー
オルソケラトロジーとは、夜寝ている間に特殊なレンズを装着することで、角膜に正しい癖(クセ)をつけて視力を改善させる方法です。
ただし、オルソケラトロジーの矯正力には限界があるので、強度乱視の矯正には向きません。
・日中は裸眼で過ごすことができる。
・手術しなくても矯正できる。
・子供でも受けることができる。
・強度乱視は治すことができない。
・睡眠時間を確保する必要がある。
・コンタクトレンズ同様に毎日ケアする必要がある。
・維持費がかかる。
・寝相(ねぞう)が悪い場合は睡眠中にレンズがズレてしまう。
オルソケラトロジーは、日中裸眼で過ごすことができるので、激しいスポーツをする人でコンタクトレンズがズレる心配がなくなります。
また、レーシック手術では、角膜を薄くスライスしてフラップという蓋(ふた)を作りますが、レーシック手術を受けた目の場合は、格闘技などの目に激しい接触が考えられるスポーツをする場合にズレてしまう心配があります。
その点、オルソケラトロジーの場合は、日中ならば何も心配せずにスポーツも生活することができます。
6.乱視の3つの予防対策方法を知ろう!
乱視から目を守る3つの予防対策方法を知っておくことが大切です。
(1)乱視対策のトレーニング
(2)目へのダメージを防ぐ
(3)眼精疲労・ドライアイの予防
(1)乱視対策のトレーニング
乱視の予防対策には、乱視対策のトレーニングが有効です。
8の字を横にしたものを目でなぞるような感じで、大きくゆっくりと眼球を動かして見ましょう。
回数の目安は、1日10回程度で昼休憩や暇な時間、夜寝る前などに行うと良いでしょう。
乱視対策のトレーニングの注意点は、コンタクトレンズやメガネを外した状態で行うことです。
例えば、コンタクトレンズをしたまま乱視対策のトレーニングをしてしまうと、コンタクトレンズが眼球から剥がれて、目の奥やズレなど危険が起こる場合があります。
乱視対策のトレーニングは、乱視だけではなく、視力回復効果も期待できます。
(2)目へのダメージを防ぐ
目を強くつぶったり、目を細めてモノを見ることを避けましょう。
目を強くつぶったり、目を細めてモノを見る行動は、角膜の歪みにつながり、乱視になる可能性を高めてしまいます。
また、まつ毛で角膜を傷つけないようにすることも大切です。
まつ毛が長くて目に入りやすい人は、まつ毛パーマなどをすると乱視の予防対策につながります。
(3)眼精疲労・ドライアイの予防
眼精疲労などでドライアイが進行すると、乱視の原因になることがあります。
ドライアイは、長時間のパソコン(PC)作業やスマートフォン(スマホ)の見過ぎなどによって、まばたきの回数と涙液の量が減少して、目の表面が乾燥した状態です。
涙液が少なくなると角膜がデコボコになって歪むことで、乱視を引き起こします、
目の乾燥を感じたら休息をとったり、目薬(点眼薬・点眼液)などで目の潤いを補給するようにしましょう。
>>>関連記事「ドライアイの原因と対策方法!実は知らない間にあなたの瞳はドライアイかもしれない?」
7.乱視の予防対策に効果的なサプリメントの選び方

乱視の原因の一つに眼精疲労がありますが、瞳孔括約筋(どうこうかつやくきん)や瞳孔散大筋(どうこうさんだいきん)に疲れが溜まると、瞳孔が緊張して小さく絞られてしまいます。
瞳孔が緊張して小さく絞られると、暗い場所でモノが見えにくくなり、余計に目が疲れるようになります。
アントシアニンには、瞳孔の働きを正常に保つ働きがあるので、眼精疲労による乱視を予防する効果があると考えられています。
アントシアニンに眼精疲労による乱視を予防する効果は、臨床試験によっても確認されています。
アントシアニンを多く含んでいるブルーベリー配合のサプリメントには、目の周囲に張り巡らされた毛細血管の血流を促進して、眼精疲労を緩和する効果もあります。
疲労から症状が現れる後天性の乱視を予防するためにも、アントシアニンは積極的に摂取すると良いでしょう。
また、アントシアニン以外にも、目の健康に優れた成分もあるので、一緒に摂取することで、相乗効果を得ることができます。
>>>関連記事「ブルーベリーに含まれているアントシアニンはどんな効果があるのか?」
目の健康に良い成分と該当する成分をまとめると、下記の表になります。
■目の健康に良い成分と該当する成分
| 目の健康に良い成分 | 該当する成分 |
| 抗酸化力の高い成分 | ルテイン、アントシアニン(ポリフェノール)、アスタキサンチン、ビタミンC、ビタミンE |
| 見た光を視神経に伝える成分 | ブルーベリー、ビルベリー、マキベリー、ミネラル、亜鉛 |
| 目の周りの筋肉の疲労を和らげる成分 | ビタミンB1、ビタミンB2、ビタミンB6、ビタミンB12、マキベリー、クロセチン、葉酸、β-カロテン |
| 紫外線・ブルーライトなどの有害な光から守る成分 | ルテイン、アスタキサンチン、ゼアキサンチン |
| 目の血行を改善する成分 | DHA、EPA、ビタミンE、クロセチン |
| 目の老化防止する成分 | アスタキサンチン、ビタミンC、コエンザイムQ10、マキベリー、 |
8.安全規格を取得しているサプリメントを選び方
毎日サプリメントを摂取し続けるためにも、安全性がしっかり守られているサプリメントを選ぶことが大切になります。
衛生管理や安全管理がしっかりしていない会社のサプリメントを摂取したくありませんよね。
安全のお墨付きがあるサプリメントを確認するには、3つの安全基準があります。
(1)有機JAS認証
(2)GMP基準
(3)HACCP(ハサップ)
(1)有機JAS認証
有機JASマークは、農薬や化学肥料などの化学物質を使用していないので、自然界の力で生産された食品にのみ付けられます。
有機食品のJAS規格に適合した生産が行われていることを登録認定機関が検査して、認定された事業者のみが有機JASマークを貼ることができます。
(2)GMP基準
医薬品の製造には、適正・製造規範の略で「GMP(Good Manufacturing Practice)」という制度があります。
原材料の受け入れ・製造・出荷のすべての家庭において、製品が「安全」で「一定の品質」が保たれるようにするための製造工程管理基準のことになります。
(3)HACCP(ハサップ)
HACCPとは、食品の中に潜む危害要因を科学的に分析し、危害要因が除去、あるいは安全な範囲まで低減できる工程を常時管理して記録することになります。
継続的に安全確認をおこなう安全管理手法で極めて高い安全性を確保している証になります。
9.「乱視の見え方・症状・原因から検査・治療方法・予防対策まで徹底解説!」まとめ

「乱視の見え方・症状・原因から検査・治療方法・予防対策まで徹底解説!」について解説してきました。
最後におさらいとして、「乱視の見え方・症状・原因から検査・治療方法・予防対策まで徹底解説!」に要点をまとめてみます。
(1)正乱視
(2)不正乱視
■3種類の正乱視の見えた方の違い
【直乱視】上下方向に潰れるように歪んで見える
【倒乱視】横方向に潰れるように歪んで見える
【斜乱視】斜め方向に潰れるように歪んで見える
■乱視の見え方
・モノが二重に見える
・モノが三重に見える
・縦や横にモノがだぶるようにブレて見える
・近くや遠くのモノがぼやけて見える
・光が滲んで見えたる
■乱視の原因は、角膜や水晶体の歪み!
■乱視の検査のことを乱視表「乱射線乱視表測定」を使用する。
■乱視の治療方法は、基本的にメガネやコンタクトレンズによる矯正する!
■最近の医療技術の発展によって、新しいソフトコンタクトレンズが発売されている!
■乱視を本格的に治療方法
(1)レーシック手術
(2)オルソケラトロジー
■乱視の3つの予防対策方法
(1)乱視対策のトレーニング
(2)目へのダメージを防ぐ
(3)眼精疲労・ドライアイの予防
■乱視に良い成分はアントシアニン!
■目の健康に良い成分と該当する成分
| 目の健康に良い成分 | 該当する成分 |
| 抗酸化力の高い成分 | ルテイン、アントシアニン(ポリフェノール)、アスタキサンチン、ビタミンC、ビタミンE |
| 見た光を視神経に伝える成分 | ブルーベリー、ビルベリー、マキベリー、ミネラル、亜鉛 |
| 目の周りの筋肉の疲労を和らげる成分 | ビタミンB1、ビタミンB2、ビタミンB6、ビタミンB12、マキベリー、クロセチン、葉酸、β-カロテン |
| 紫外線・ブルーライトなどの有害な光から守る成分 | ルテイン、アスタキサンチン、ゼアキサンチン |
| 目の血行を改善する成分 | DHA、EPA、ビタミンE、クロセチン |
| 目の老化防止する成分 | アスタキサンチン、ビタミンC、コエンザイムQ10、マキベリー、 |
■3つの安全基準
(1)有機JAS認証
(2)GMP基準
(3)HACCP(ハサップ)
最後までお読みいただきありがとうございました!