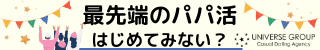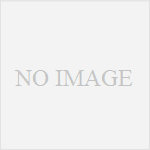このページは、「アサリにはオルニチンが含まれているのか?シジミとどっちが肝臓に効果的なのか?」について、わかりやすく解説していきますので、参考にしてもらうためにお伝えしていきます。
オルニチンは、シジミや本しめじに多く含まれている栄養成分で、肝臓の働きをサポートしてくれて、二日酔いや疲労回復に効果があることで有名です。
オルニチンには、弱まった肝臓をサポートして、正常化と回復の促進に役立ちます。
シジミと同様に貝類で、よく食べることが多いアサリにもオルニチンは含まれているのでしょうか?
では、「アサリにはオルニチンが含まれているのか?シジミとどっちが肝臓に効果的なのか?」について詳しく解説していきます。
1.アサリにはオルニチンが含まれているのか?
アサリは、パスタや汁物などの料理の食材(食品)として利用されていて、カルシウムや亜鉛などの栄養成分を多く含んでいる貝です。
特にアサリは、ビタミンB12の含有量は貝類の中でもズバ抜けて含まれています。
では、栄養素たっぷりのアサリですが、シジミのように豊富なオルニチンは含まれているのでしょうか?
■アサリのオルニチンは極微量しか含まれていない!
アサリとシジミは、味や食感だけではく、見た目にも共通したところがありますが、アサリにはほとんどオルニチンが含まれていません。
アサリだけに限らずに、ハマグリやムール貝といった他の種類の貝に含まれているオルニチン含有量は極微量になります。
オルニチンを貝類から摂取するのであれば、シジミ以外には考えられません。
肝機能の向上に効果があるオルニチンは、私たちの有害であるアンモニアの解毒をサポートしてくれるので、疲労回復効果や代謝アップ、二日酔い予防、美肌・美容効果にダイエットなど幅広い作用が報告されています。
しかし、アサリには、私たちの身体に作用があるオルニチンがほとんど含まれていないので、オルニチンによる肝機能サポート効果は期待できません。
アサリには、オルニチンの代わりに「タウリン」という肝機能を促進してくれるアミノ酸成分が豊富に含まれているので、オルニチンが微量であっても肝機能の向上が期待できます。
タウリンは、別名アミノエチルスルホン酸と呼ばれています。
■アサリにはタウリンが豊富に含まれている!
タウリンは、オルニチンと同じような効果が期待できる成分です。
タウリンとは、貝の旨味を決定づける成分と言っても過言ではありません。
タウリンの含有量によって貝の味が変化することになります。
タウリンの効果は、肝機能の促進だけではなく、アルコール障害の改善、血液をサラサラにしてくれたり、コレステロール値や血糖値を下げてくれる効果も期待できることから「脂肪肝の予防」や「生活習慣病の予防」にも効果が期待できます。
【タウリン】421mg
【カルシウム】66mg
【カリウム】140mg
【亜鉛】1.0mg
【鉄】3.8mg
【ビタミンB12】52.4ug
アサリ100g中に含まれているタウリンの量は、約421mgになります。
アサリのタウリンの含有量は、貝類の中でも豊富に含まれています。
タウリンは、魚介類を中心に多く含まれているの成分になりますが、実はアサリより多くのタウリン含有量を誇る貝が「牡蠣(かき)」になります。
牡蠣に含まれているタウリンの量は、魚介類の中でも断トツの含有量の100gあたり約1200mgになります。
しかし、牡蠣は価格的にもやや高価で毎日食べることが難しいので、継続的にタウリンを食品(食材)から摂取したい場合は購入しやすいアサリを活用すると良いでしょう。
さらに、アサリは料理のレパートリーも多くあり、「味噌汁」「アクアパッツア」「パスタ」「酒蒸し」など飽きずにアサリを食べることができます。
2.オルニチンを摂取するならアサリではなくシジミが最適!
アサリにもシジミにも肝機能をサポートするというアミノ酸成分が含まれていますが、疲労回復や二日酔い予防に高い効果が期待できるオルニチンを摂取するのであれば、アサリよりシジミが最適です。
■そもそもアサリとシジミの違いとは?
アサリに多く含まれているタウリンは、食べ物の消化吸収を助ける胆汁の分泌を促進させてくれたり、肝細胞を活性酸素から守って肝機能を高めてくれる働きがあります。
また、胆汁は肝臓から分泌されるので、胆汁の分泌を促進するためには、肝臓全体の機能向上を図らなければいけません。
タウリンには、肝臓の機能を全体的に向上させてくれる効果が期待できる成分になります。
シジミに多く含まれているオルニチンも肝機能の向上に役立つとされているアミノ酸成分になりますが、タウリンとの決定的な違いは、NADH(ニコチンアミドアデニンジヌクレオチド)の消費を促進させることができるということです。
NADH(ニコチンアミドアデニンジヌクレオチド)とは、二日酔いの原因となっているアセトアルデヒドという物質と体内に残っているアルコールが代謝される過程で作られる物質ですが、NADH(ニコチンアミドアデニンジヌクレオチド)が過剰に発生してしまうと脳に必要なエネルギーが送られずに、疲労感の蓄積や二日酔いの悪化にもつながってしまいます。
オルニチンは、アンモニアを解毒する過程でNADH(ニコチンアミドアデニンジヌクレオチド)の消費を間接的に促進する働きがあるので、お酒をよく飲む人には最適な成分といえます。
アサリは肝機能を総合的に高めたい人向けで、シジミはお酒をよく飲む人向けにオススメの成分ともいえます。
■冷凍シジミはオルニチン含有量を約8倍になる!
オルニチンは、解毒を促進させることで、「二日酔い予防」「美肌・美容」「疲労回復」など様々な効果があります。
オルニチンを多く含んでいる貝類は、シジミが1番になりますが、シジミに含まれているオルニチン量は100gあたり約15mgになります。
一般的に、オルニチンの1日の目安摂取量は400mg〜1000mgといわれています。
オルニチン400mg〜1000mgは、シジミで換算すると約933個〜約2333個の量を食べる必要があります。
(※算出方法は、シジミ100g中にオルニチン15mg、シジミ35個分が100gの計算しています。)
1日3食シジミ汁を作ったところで、到底約933個〜約2333個ものシジミを使用することはできません。
このような時にオススメしたいのが、シジミを冷凍することによって、シジミのオルニチン含有量を約8倍以上に増加させることができます。
シジミに含まれているオルニチンは、100gあたり約15mg(シジミ約35個分)とされているので、冷凍することで100gあたり120mgのオルニチン量にアップします。
冷凍シジミなら1日500g前後を食べることで、十分すぎるオルニチン量を摂取することができるようになるので、シジミを食べる時は一旦冷凍してから調理するようにしましょう。
3.シジミのオルニチンを8倍にする冷凍保存方法
家庭でも簡単にできる「シジミの冷凍保存方法」を紹介します。
【1】パックからシジミをザルに出して、水道水の流水で優しく揉み洗いする。
【2】平らなバットなどにしじみが重ならないように広げて置く。
【3】貝殻が水面からほんの少し顔を出すくらいの量の水道水を入れる。(1%の塩水でもOK)
【4】バットの上に新聞紙や本などを被せて、光をさえぎるように常温で3時間程度放置して砂を吐かせる。(冬場は5時間程度)
【5】砂抜き後のシジミで、口が半開きになったり、触っても貝が閉じないといった場合は、すでにシジミは死んでいるので捨てる。
【6】砂抜き後のシジミをザルに出して、流水で軽く洗う。
【7】使う分量づつシジミを小分けして新聞紙に包んだら、さらにジップロックなどのビニール袋に入れる。
【8】ビニール袋に入れたシジミをマイナス18度以下の冷凍庫でゆっくりと時間をかけて凍らせる。
【9】凍ったまま料理に使用する。
オルニチン含有量を増やすための冷凍保存のポイントは、とにかくゆっくりと時間をかけてしじみを凍らせることです。
シジミを新聞紙に包むことで、冷凍されるまでにかかる時間を伸ばせるので、必ず新聞紙に包んでから冷凍保存をすることが重要になります。
また、砂抜きシジミを使用する場合は、【1】〜【4】の工程は飛ばしてもらっても問題ありませんので、工程【6】から始めましょう。
シジミのオルニチン含有量も増えて、保存もしっかりできて、かなり便利で活用しやすい方法です。
4.もっとオルニチンを手軽に摂取するにはオルニチン配合のサプリメントが効率的!
アサリもシジミも肝臓に良いとされている成分が豊富に含まれている貝です。
しかし、どんなに豊富な栄養成分が含まれている貝類でも、「毎日たくさんの量を食べること」「仕事やプライベートが忙しい」「料理が苦手」など、人それぞれ理由があるので、現実的に難しいと思います。
シジミから抽出されたオルニチンがたっぷり配合されているサプリメントが多く販売されています。
さらに、オルニチンと一緒に摂取すると相乗効果が狙える成分も同時に摂取できるので効率的です。
サプリメントなら豊富なオルニチンを効率良く摂取できるだけではなく、カルシウムや亜鉛、鉄、ビタミン類などの様々な栄養素も一種に配合されているものがほとんどなので、オルニチン効果+αで健康や美容面をさらに効果を高めてくれます。
肝機能の衰えが気になる中高年の人はもちろんのこと、オルニチンには「筋力増強」「ダイエット効果」「美肌・美容効果」「ストレス解消効果」なども報告されているので、美容に敏感な女性やストレスを感じやすく悩んでいる人にも効果的に摂取できるオルニチン配合のサプリメントがオススメです。
オルニチン配合のサプリメントには、錠剤タイプ・ゼリータイプ・ドリンクタイプなど様々な種類のサプリメントが販売されています。
自分の好みや目的によって、オルニチン配合のサプリメントを選ぶことができます。
5.オルチニンに副作用があるのか?
オルニチンは、そもそも体内で生成される成分であるので、外部からのオルニチンも問題なく体内で役立つとされています。
オルニチン自体に副作用の心配は、基本的にありませんが、過剰摂取による副作用が絶対にないとは言いきれません。
オルニチンは1日10g以上を過剰摂取してしまうと、胃痛や下痢などの症状が現れることがあります。
・胃痛
・下痢
6.オルニチン配合のサプリメントを効果的に摂取するタイミングとは?
オルニチンを効率的に摂取する方法は、サプリメントから手軽に栄養補給ができます。
世の中には、様々なサプリメントがありますが、一般的に販売されているサプリメントは医薬品と異なり、摂取タイミングは厳密に決められていません。
つまり、人それぞれの摂取タイミングでサプリメントを摂取指定も健康上の問題はありません。
では、一体いつオルニチンを摂取するとサプリメントの効果が発揮されやすいのでしょうか?
(1)空腹時(食前)
(2)就寝前
(3)飲酒した直後か翌朝
(4)運動前か運動後
(1)空腹時(食前)
サプリメントに限らず食べ物全般に言えることですが、基本的に空腹時に食べたものの成分は、体内で早く吸収しやすいので、サプリメントも同様に空腹時に摂取するのが理想的です。
しかし、胃がもともと弱い人や、胃が荒れやすい人は、胃痛の症状を起こす可能性があるので、空腹時(食前)ではなくて食後に摂取するようにしましょう。
(2)就寝前
就寝中(特に22時〜2時の間)はゴールデンタイムといわれていて、体の成長・肌の生成・疲労回復のための休息など、健康的な体作りには欠かせいない時間であるので、就寝前にオルニチンのサプリメントを摂取することによって、より効率的に成分が働き、翌朝スッキリと目覚めることができます。
また、オルニチンのサプリメントの効果をより感じやすくするためには、夕食をできるだけ早い時間に食べるか、消化の良いものを食べることが良いでしょう。
血糖値が下がりきるタイミング(食後から6〜8時間後)にサプリメントを摂取して、就寝するとうことがベストではありませんが、忙しいとなかなか実現しにくことでしょう。
そのため、なるべく消化の良いうどんやおかゆなどを食べるのも良いでしょう。
(3)飲酒した直後か翌朝
お酒(アルコール)を飲みすぎた直後にサプリメントを摂取すると、オルニチンがより肝臓の働きをサポートしてくれます。
ただ、もともとお酒が弱い体質で、二日酔いになりやすいということで荒れば、飲酒前にオルニチンのサプリメントを摂取すると良いでしょう。
(4)運動前か運動後
運動前にオルニチンのサプリメントを摂取することで、代謝を良くして脂肪燃焼やダイエットに効果があります。
運動後にオルニチンのサプリメントを摂取することで、疲労回復を早める効果があります。
7.安全規格を取得しているサプリメントを選び方
毎日サプリメントを摂取し続けるためにも、安全性がしっかり守られているサプリメントを選ぶことが大切になります。
衛生管理や安全管理がしっかりしていない会社のサプリメントを摂取したくありませんよね。
安全のお墨付きがあるサプリメントを確認するには、3つの安全基準があります。
(1)有機JAS認証
(2)GMP基準
(3)HACCP(ハサップ)
(1)有機JAS認証
有機JASマークは、農薬や化学肥料などの化学物質を使用していないので、自然界の力で生産された食品にのみ付けられます。
有機食品のJAS規格に適合した生産が行われていることを登録認定機関が検査して、認定された事業者のみが有機JASマークを貼ることができます。
(2)GMP基準
医薬品の製造には、適正・製造規範の略で「GMP(Good Manufacturing Practice)」という制度があります。
原材料の受け入れ・製造・出荷のすべての家庭において、製品が「安全」で「一定の品質」が保たれるようにするための製造工程管理基準のことになります。
(3)HACCP(ハサップ)
HACCPとは、食品の中に潜む危害要因を科学的に分析し、危害要因が除去、あるいは安全な範囲まで低減できる工程を常時管理して記録することになります。
継続的に安全確認をおこなう安全管理手法で極めて高い安全性を確保している証になります。
8.「アサリにはオルニチンが含まれているのか?シジミとどっちが肝臓に効果的なのか?」まとめ
「アサリにはオルニチンが含まれているのか?シジミとどっちが肝臓に効果的なのか?」について解説してきました。
最後におさらいとして、「アサリにはオルニチンが含まれているのか?シジミとどっちが肝臓に効果的なのか?」に要点をまとめてみます。
■アサリにはタウリンが豊富に含まれている!
■アサリ100gあたりに含まれている成分表
【タウリン】421mg
【カルシウム】66mg
【カリウム】140mg
【亜鉛】1.0mg
【鉄】3.8mg
【ビタミンB12】52.4ug
■オルニチンを摂取するならアサリではなくシジミが最適!
■冷凍シジミはオルニチン含有量を約8倍になる!
■もっとオルニチンを手軽に摂取するにはオルニチン配合のサプリメントが効率的!
■オルニチンの摂取量
【1日の目安摂取量】400mg〜1000mg
【1日の上限摂取量】10g以上
■オルニチン自体に副作用の心配は、基本的にありませんが、過剰摂取による副作用が絶対にないとは言いきれません!
■オルニチンの過剰摂取による副作用の症状
・胃痛
・下痢
■3つの安全基準
(1)有機JAS認証
(2)GMP基準
(3)HACCP(ハサップ)
最後までお読みいただきありがとうございました!