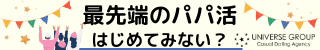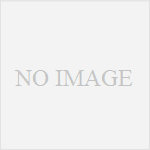このページは、「オルニチンは冷え性の改善に効果があるのか?副作用はあるのか?」について、わかりやすく解説していきますので、参考にしてもらうためにお伝えしていきます。
オルニチンは、シジミや本しめじに多く含まれている栄養成分で、二日酔いや疲労回復に効果があることで有名です。
「冷え性」で悩んでいる方は、年々増加傾向にあります。
最近、「冷え性」は女性だけではなくて、男性でも悩んでいる方が多くなってきています。
冷え性は、寒さが辛いだけではなく、代謝や免疫力が低下してしまうことで、冷えは万病の元
といわれるくらい健康にも悪影響を与えてしまいます。
冷え症を改善するためには、もちろん血行を良くすることを考えるのも大事ですが、意外と知られていないのが肝臓と冷えとの関係です。
肝臓を元気にしてくれるアミノ酸の一種であるオルニチンを摂取することで、冷えが改善されたという実験結果があります。
では、「オルニチンは冷え性の改善に効果があるのか?副作用はあるのか?」について詳しく解説していきます。
1.冷え性が肝臓の疲れから現れている可能性がある!
女性の多くは、冷え性に悩んでいる方が多く、服装に気を使ってみたり、厚手の靴下を履いたり、食事に生姜(ショウガ)を取り入れあたり、白湯を飲んだり、様々な冷え性対策をしていると思います。
実は、肝臓が疲労している時にも、冷え性と同じような症状が起こることがあります。
肝臓は「沈黙の臓器」と呼ばれているので、大きな症状が現れていなくても、実は小さな症状はサインとして現れています。
ただ、他の症状と見分けがつきにくいため見逃しやすい傾向にあります。
よく肌の色が黄色っぽくなると、「肝臓が悪い?」と疑ったりという話があります。
これと同じようなことが他にもあります。
貧血のような症状になったり、冷えを感じたりの症状が現れたりします。
また、爪の色も黄色っぽくなったりもします。
女性によくある冷え性は、体が冷えてしまうと血行が悪くなってしまい、冷えを感じてしまいます。
冷え性の原因が肝臓にある場合は、肝臓が疲れてしまい、肝臓自体が血行不良になっている状態で、肝臓が正常に働いていません。
このような場合は、肝臓を温めてあげることが大切になります。
肝臓の位置がわかない方もいると思いますが、肝臓はみぞおちの右側にあり、助骨に隠れているので、湯たんぱやカイロをみぞおちの右側に当ててあげることで、肝臓が温まります。
2.オルニチンは冷え性の改善に効果があるのか?
オルニチンは、冷え性の改善に効果があります。
オルニチンは、肝臓に効果がある成分として知られているので、二日酔い対策などで有名ですが、なぜ冷え症も改善できるのでしょうか?
肝臓が熱を作り出す器官でもあるからと考えられています。
肝臓は、体温を一定にキープルするために多くの発熱量を持つ部分でもあり、発熱量は全体の30%ともいわれています。
基礎対応を上げて、冷え症を改善するには、運動をしたりして血行を良くすることも大切ですが、肝臓の機能をアップさせることが効果的です。
3.冷え性の改善に効果的なオルニチン摂取方法
冷え性を改善するには、オルニチンを上手に摂取して、肝臓の働きを良くしてあげる工夫が必要になります。
肝臓が正常にに働くことができるようになると、肝臓の血行も回復した結果、体の冷え性も軽減されていくことが期待できます。
また、オルニチンには、成長ホルモンを活性化するサポートしてくれるので、新陳代謝がアップして冷え性の改善にもつながります。
オルニチンは、サプリメントでも摂取できますが、サプリメントを摂取するのが心配の方は、シジミなどの食品(食材)から摂取することができます。
シジミの他にもチーズやキノコ類などにも微量ですが含まれています。
冷え性がなかなか治らない方は、オルニチンを試すと良いでしょう。
4.オルニチン摂取と+αで冷え症を改善するには?
オルニチンを摂取するのと一緒に+αで冷え性の改善に役立つことがあります。
(1)血流を良くする
(2)食事で冷え症を改善
(1)血流を良くする
血流を良くして冷え性を改善するには、ストレッチをしたり、マッサージをするなどでも有効ですが、肝臓を温めることで血流をアップさせることもできます。
冷え性には、半身浴・湯たんぽ・腹巻などで肝臓を温めることで、血流を良くして生きましょう。
肝臓は全身の40%もの血液を運ばれてくる場所でもあります。
血流を改善することで、浮腫(むくみ)の悩みも解消することができます。
(2)食事で冷え症を改善
冷え性の改善として有名なのが、体を温める生姜(ショウガ)やエキストラバージンオリーブ、唐辛子などがありますが、肝機能をアップさせるためにはオルニチンが効果的です。
オルニチンを多く含む食品(食材)としては、シジミが有名ですが、実はシジミには体を冷やす食品(食材)でもあります。
東洋医学の考えでは、体を温める「陽」の食品(食材)、体から熱を奪ってしまう「陰」の食品(食材)、どちらでもない「平」の食品(食材)に分類されますが、シジミはこの中の「陰」の食品(食材)に入っています。
そのため冷え性対策としては、シジミからではなくサプリメントからオルニチンを摂取する方が良いでしょう。
5.オルニチンの科学的や医学的な根拠はあるのか?
オルニチンが冷え性の改善に効果があるといわれています。
しかし、「本当にオルニチンが冷え性の効果に根拠があるのか?」と疑問に思いますよね。
では、実際にオルニチンが冷え性に効果が科学的や医学的な根拠があるのか調べて見ました。
協和発酵バイオ株式会社の実験によると、1日800mgのオルニチンを摂取するグループとプラセボ群(偽薬群・無知療群)を摂取するグループを比較したところ、オルニチンを摂取したグループは、疲労回復や美肌・美容効果だけではく、手足の冷えが改善されたという結果があります。
6.オルニチンを多く含んでいる食品(食材)
オルニチンが多く含まれている食品(食材)として、シジミなどの貝類・魚介類・キノコ類などがあげられます。
オルニチンが多く含まれている食品(食材)を紹介していきます。
(100g中のオルニチン含有量:オルニチン100g相当の量)
【本しめじ】160mg:約0.5袋
【シジミ】10.7〜15.3mg :約35個
【ヒラメ】0.6〜4.2mg :約1切れ
【キハダマグロ】1.9〜7.2mg:刺身7〜10切れ
【チーズ】0.8〜8.5mg:約5枚(スライスチーズ)
【えのき茸】14.0mg:約1.2袋
オルニチンといったら、シジミと答える方が多いと思いますが、キノコ類のオルニチン含有量もあなどれません。
オルニチンの含有量No.1の本しめじなら、シジミの10倍以上も含まれています。
(100g中のオルニチン含有量:シジミに換算した個数「シジミ1個あたり0.4mgで換算」)
【本しめじ】160mg:約400個
【ブナしめじ】140mg:約350個
【ブナピー】110mg:約275個
【霜降りひらたけ】50mg:約125個
【エリンギ】30mg:約75個
【えのき茸】14mg:約35個
【舞茸(マイタケ)】10mg:約25個
最近、コンビニやスーパーなどでよく見かけるのが、「シジミ◯◯個分のオルニチン入り!」などと表示されている加工食品です。
味噌汁やスープ類が多くありますが、インスタントラーメンにシジミが入っています。
(オルニチン含有量:単位「シジミ1個あたり0.4mgで換算」)
【キリン・ウコンとしじみ900個分のオルニチン】400mg:100ml入りビン
【マルコメ・貝だし液みそ】68mg:一杯あたり
【日清・香るしじみだし醤油ラーメン】30mg:1個
【トップバリュ・オルニチン入ウコン顆粒】50mg:1袋
【トップバリュ・しじみわかめスープ】37mg:一杯あたり
【ひかり味噌・元気プラスオルニチン入りおみそ汁】37mg:一杯あたり
【永谷園・しじみ70個分のちから】25mg:一杯あたり
【ヒゲタ・しじみ醤油】12mg:大さじ一杯(15ml)
【トーノー・オルニチン入さんぴん水】10mg:100mlあたり
7.オルニチンの1日の目安摂取量と上限摂取量はどのくらい?
【1日の目安摂取量】400mg〜1000mg
【1日の上限摂取量】10g以上
一般的に、オルニチンの1日の目安摂取量は400mg〜1000mg程度といわれています。
シジミに含まれているオルニチンの量は100g中に10.7〜15.3mg 、本しめじでも100g中に160mg程度ですので、オルニチンを多く含む食品(食材)を組み合わせても、普段の食事からの摂取では過剰になることがほとんどありません。
むしろ、食品(食材)から1日のオルニチン目安摂取量を満たす方が難しいです。
オルニチンの上限摂取量は、1日10g以上を摂取した際に、下痢や胃痛といった症状が現れたという報告があります。
1日10g以上を摂取すると下痢や胃痛といった症状から、オルニチンの過剰摂取で重篤な副作用の症状は起こりにくいもの、軽度の消化器官系炎症が引き起こる可能性があります。
8.オルチニンに副作用があるのか?
オルニチンは、そもそも体内で生成される成分であるので、外部からのオルニチンも問題なく体内で役立つとされています。
オルニチン自体に副作用の心配は、基本的にありませんが、過剰摂取による副作用が絶対にないとは言いきれません。
オルニチンは1日10g以上を過剰摂取してしまうと、胃痛や下痢などの症状が現れることがあります。
・胃痛
・下痢
9.安全規格を取得しているサプリメントを選び方
毎日サプリメントを摂取し続けるためにも、安全性がしっかり守られているサプリメントを選ぶことが大切になります。
衛生管理や安全管理がしっかりしていない会社のサプリメントを摂取したくありませんよね。
安全のお墨付きがあるサプリメントを確認するには、3つの安全基準があります。
(1)有機JAS認証
(2)GMP基準
(3)HACCP(ハサップ)
(1)有機JAS認証
有機JASマークは、農薬や化学肥料などの化学物質を使用していないので、自然界の力で生産された食品にのみ付けられます。
有機食品のJAS規格に適合した生産が行われていることを登録認定機関が検査して、認定された事業者のみが有機JASマークを貼ることができます。
(2)GMP基準
医薬品の製造には、適正・製造規範の略で「GMP(Good Manufacturing Practice)」という制度があります。
原材料の受け入れ・製造・出荷のすべての家庭において、製品が「安全」で「一定の品質」が保たれるようにするための製造工程管理基準のことになります。
(3)HACCP(ハサップ)
HACCPとは、食品の中に潜む危害要因を科学的に分析し、危害要因が除去、あるいは安全な範囲まで低減できる工程を常時管理して記録することになります。
継続的に安全確認をおこなう安全管理手法で極めて高い安全性を確保している証になります。
10.「オルニチンは冷え性の改善に効果があるのか?副作用はあるのか?」まとめ
「オルニチンは冷え性の改善に効果があるのか?副作用はあるのか?」について解説してきました。
最後におさらいとして、「オルニチンは冷え性の改善に効果があるのか?副作用はあるのか?」に要点をまとめてみます。
■オルニチンは冷え性の改善に効果がある!
■オルニチン摂取と+αで冷え症を改善に役立つ!
(1)血流を良くする
(2)食事で冷え症を改善
■オルニチンが多く含まれている食品(食材)
(100g中のオルニチン含有量:オルニチン100g相当の量)
【本しめじ】160mg:約0.5袋
【シジミ】10.7〜15.3mg :約35個
【ヒラメ】0.6〜4.2mg :約1切れ
【キハダマグロ】1.9〜7.2mg:刺身7〜10切れ
【チーズ】0.8〜8.5mg:約5枚(スライスチーズ)
【えのき茸】14.0mg:約1.2袋
■オルニチンの摂取量
【1日の目安摂取量】400mg〜1000mg
【1日の上限摂取量】10g以上
■オルニチン自体に副作用の心配は、基本的にありませんが、過剰摂取による副作用が絶対にないとは言いきれません!
■オルニチンの過剰摂取による副作用の症状
・胃痛
・下痢
■3つの安全基準
(1)有機JAS認証
(2)GMP基準
(3)HACCP(ハサップ)
最後までお読みいただきありがとうございました!