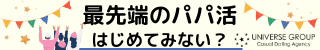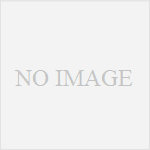このページは、「オルニチンは疲労回復に効果があるのか?副作用はあるのか?」について、わかりやすく解説していきますので、参考にしてもらうためにお伝えしていきます。
身体の疲れを取るための食べ物やサプリメントを探すと「オルニチン」という言葉をみかけます。
オルニチンは、シジミや本しめじに多く含まれている有名な栄養成分になります。
しかし、なぜ疲労回復に効果があるといわれているのでしょうか?
では、「オルニチンは疲労回復に効果があるのか?副作用はあるのか?」について詳しく解説していきます。
1.オルニチンは疲労回復に効果があるのか?
結論から言うと、オルニチンには疲労回復に効果があります。
しかし、なぜオルニチンを摂取することで、たくさん寝ても疲れが取れないような疲労感を軽減させられのでしょうか?
オルニチンが疲労回復効果をもたらす理由とメカニズムについて解説していきます。
(1)解毒作用が促進されるため!
(2)エネルギー産生が円滑に進むため!
(1)解毒作用が促進されるため!
私たち人間は、「なぜ疲労感を感じるようになるのでしょうか?」ということからお話をしていきます。
毎日の食生活や生活習慣の乱れが起こることで、肝臓機能が低下してしまい、疲労を体内に溜め込んでしまうことが原因と考えられています。
肝臓機能が低下すると、肝臓の主な役割であるアンモニアの解毒が円滑に進められなくなります。
アンモニアとは、私たちの身体にとって非常に有害物質であるため、通常は肝臓の解毒作用で無毒な尿素に変換されます。
しかし、肝臓機能が低下して解毒作用が弱まっている状態では、有害物質であるアンモニアが解毒されないまま体内に残ってしまいます。
体内に残ったアンモニアは、私たちが活動するためのエネルギー産生を阻害してしまうことから、「身体がだるい」「朝起きられない」「疲れが取れない」などの疲労感の蓄積につながります。
オルニチンには、疲労感の原因であるアンモニアの解毒をサポートしてくれる効果があるので、解毒を円滑に進めることができない肝臓に代わって、アンモニアを無毒の尿素に変換して、体外へ排出してくれます。
肝臓機能が低下して解毒作用がスムーズに進めらない人にとって、まさにオルニチンは身体の内部における救世主といっても良い成分です。
(2)エネルギー産生が円滑に進むため!
オルニチンによってアンモニアの解毒がスムーズに進めていくことで、私たちの身体に必要不可欠なエネルギーを効率良く生み出すこともできます。
肝細胞内にあるミトコンドリアでは、TCAサイクル(クエン酸回路)と呼ばれているエネルギー産生回路によって、エネルギーが絶えず産生されています。
エネルギー産生が正常に行われてこそ、脳や身体に必要なエネルギーが送られて、スムーズに身体を動かすことができたり、脳がしっかりと機能することができます。
有害物質であるアンモニアには、TCAサイクル(クエン酸回路)のバランスを乱して、エネルギー産生能力を低下させてしまう作用があります。
TCAサイクル(クエン酸回路)のバランスを乱すことから、オルニチンの働きによって、有害物質であるアンモニアの解毒を手助けすることこそ、原動力の源となるエネルギーを生み出すことにつながります。
2.肝臓と疲労回復の関係
オルニチンには、アンモニアの解毒をサポートすることで、肝臓機能を向上させて、エネルギーの産生も円滑に進みます。
このようなことから、疲労と肝臓はとても深い関わり合いを持っているだけではなく、肝臓機能の低下は様々な症状を発症させてしまう可能性があります。
肝臓機能の役割とオルニチンサイクル(尿素回路)と呼ばれている解毒回路について解説していきます。
(1)オルニチンサイクル(尿素回路)の働きとは?
(2)オルニチンサイクル(尿素回路)を促進させるメリットとは?
(1)オルニチンサイクル(尿素回路)の働きとは?
オルニチンサイクル(尿素回路)とは、肝細胞内のミトコンドリアが働いているアンモニアの解毒工程のことをいいます。
代謝や運動などによって、発生したアンモニアが肝臓内のオルニチンと反応して、無毒な尿素に変換されて、体外へ排出されます。
そして、オルニチンサイクル(尿素回路)で注目する点は、アンモニアが尿素に変換される際に、オルニチンが生成されるということです。
解毒される過程で生成されたオルニチンは、再び新たなアンモニアを解毒するために、再利用されるという、効率的なシステムがオルニチンサイクル(尿素回路)に成り立っています。
【1】オルニチンがアンモニアと反応
【2】アンモニアが尿素に変換される
【3】新たなオルニチンが生成される
【1】オルニチンがアンモニアと反応
このような流れで解毒された尿素は、体外へ排出されて、生成されたオルニチンはまた解毒のためにサイクルのトップに戻ることが、オルニチンサイクル(尿素回路)になります。
(2)オルニチンサイクル(尿素回路)を促進させるメリットとは?
オルニチンサイクル(尿素回路)を促進させることは、解毒をスムーズにすることです。
さらに、肝臓の機能を高めることといっても過言ではありません。
解毒がスムーズに進むことでエネルギーは、効率良く生み出され、身体は軽やかで疲れ知らずにつながります。
エネルギーの産生がスムーズに進むと、新しく発生したアンモニアの解毒も円滑に進むので、さらに身体が軽やかで疲れしれずという好循環になります。
オルニチンサイクル(尿素回路)を促進させることによって、アンモニアを迅速に解毒することができれば、その分で肝臓機能が向上するので、疲労回復だけではなくストレス軽減・二日酔い対策・美肌美容・ダイエットなど、様々な効果が期待できると考えられています。
3.オルニチンはどんな疲労に効果があるのか?
オルニチンは、疲労回復効果があるといっても、疲労の種類も一つだけではありません。
オルニチンの働きによって、軽減することのできる疲労には、一体どのような種類があるのでしょうか?
では、オルニチンの疲労回復効果の種類について解説していきます。
(1)精神的疲労・ストレスの軽減
(2) 疲労臭軽減
(3)二日酔い・アルコール性の疲労軽減
(4)運動による疲労軽減
(1)精神的疲労・ストレスの軽減
オルニチンの疲労回復効果が現われやすいのは、精神的疲労という実験結果の報告があります。
あらかじめオルニチンを摂取することによって、「蓄積されたストレスの軽減」と「ストレスが蓄積されるのを防いでくれる」というダブルの効果が期待できます。
オルニチンの高いアンモニア解毒作用の働きで、肝臓機能が向上して、エネルギーの産生がスムーズに進められるようになった結果、「ぐっすりと質の高い睡眠がとれるようになった!」や「気分が落ち着くようになってきた!」など身体に変化が現れたことも報告されいます。
ストレス状態が低いと、自然と活動的になれたり、ストレスに負けない体質に変化していくというケースも多くみられます。
オルニチンには、肉体の溜まった疲労を回復させるだけではなく、精神的疲労に効果が期待できることから、直ぐにストレスを感じやすい人には、ぜひオルニチンを摂取して実感していただきたいです。
(2) 疲労臭軽減
慢性的に疲労が蓄積してしまっている人が、発している疲労臭という臭いがあることを知っていますか?
疲労臭の原因は、解毒しきれずに体内に残ってしまったアンモニアになります。
アンモニアの臭いは、鼻にツーンと刺さるような独特の悪臭として知られていますが、実は疲労が蓄積している人の体臭や口臭は、アンモニア臭いことがわかっています。
体内に残留しているアンモニアが血液を介して全身へ運ばれると、肺を通して「吐息」として臭いを発生したり、汗腺を通して「体臭」として、きついアンモニア臭を発生させてしまいます。
疲労臭を軽減させるためには、疲労臭の原因となっているアンモニアを解毒して、体外に排出する他ありません。
慢性的な疲労を感じているだけではなく、「なんか息が臭い!」や「体臭が気になる!」という方は、オルニチンを積極的に摂取することで、体内に残留しているアンモニアを解毒して、疲労臭の原因を根本的に解決することが大切になります。
(3)二日酔い・アルコール性の疲労軽減
オルニチンには、疲労回復効果の他にも、高いアルコール分解作用があるといわれています。
アルコール分解作用といっても、体内に入ってきたアルコールを直接分解するのではなく、アルコールが代謝される過程で発生するアセトアルデヒドという物質の代謝を促進させる効果があります。
アセトアルデヒドは、「頭が痛い」「吐き気がする」「身体が重い」といった二日酔い症状の原因となっている物質で、アンモニアと同様に私たちの身体にとって非常に有害な物質になります。
アセトアルデヒドは、ミトコンドリアを傷つけて、エネルギーを産生する回路であるTCAサイクル(クエン酸回路)に悪影響を与えてしまいます。
TCAサイクル(クエン酸回路)に悪影響が起こると、脳や各細胞にエネルギーが運ばれにくくなる結果、「頭が痛い」「吐き気がする」「身体が重い」といった二日酔い症状が発生してしまいます。
オルニチンの働きでアンモニアがスムーズに解毒されることで、二日酔いの原因になる有害物質の代謝も促進されて、エネルギー産生を阻害する要因が取り除かれます。
エネルギーが迅速に生み出されれることで、身体や脳にも送られるエネルギーも増えるので、二日酔いやアルコール性の疲労軽減にも効果が期待できます。
(4)運動による疲労軽減
私たちの身体にとって有害物質であるアンモニアは、実は運動することによっても大量に発生してしまいます。
筋肉やエネルギーの消耗によって発生したアンモニアは、運動後の疲労感につながるだけではなく、運動中のパフォーマンスを低下させることにもつながります。
「運動後の筋肉痛を予防したい!」や「運動中すぐに疲れてしまう!」という人が、オルニチンを摂取すると疲労軽減の効果があります。
運動による疲労軽減に効果あるというのも、オルニチンには、「運動によるアンモニア上昇を抑制する」や「運動パフォーマンスの低下を防ぐ」という効果が示されているからです。
運動中のパフォーマンス低下を防止したい場合は、「運動前」にオルニチンを摂取することが効果的です。
運動後の疲労を予防したい場合は、「運動後」にオルニチンを摂取することが効果的です。
4.オルニチンを多く含んでいる食品(食材)
オルニチンが多く含まれている食品(食材)として、シジミなどの貝類・魚介類・キノコ類などがあげられます。
オルニチンが多く含まれている食品(食材)を紹介していきます。
(100g中のオルニチン含有量:オルニチン100g相当の量)
【シジミ】10.7〜15.3mg :約35個
【ヒラメ】0.6〜4.2mg :約1切れ
【キハダマグロ】1.9〜7.2mg:刺身7〜10切れ
【チーズ】0.8〜8.5mg:約5枚(スライスチーズ)
【えのき茸】14.0mg:約1.2袋
オルニチンといったら、シジミと答える方が多いと思いますが、キノコ類のオルニチン含有量もあなどれません。
オルニチンの含有量No.1の本しめじなら、シジミの10倍以上も含まれています。
(100g中のオルニチン含有量:シジミに換算した個数「シジミ1個あたり0.4mgで換算」)
【本しめじ】160mg:約400個
【ブナしめじ】140mg:約350個
【ブナピー】110mg:約275個
【霜降りひらたけ】50mg:約125個
【エリンギ】30mg:約75個
【えのき茸】14mg:約35個
【舞茸(マイタケ)】10mg:約25個
最近、コンビニやスーパーなどでよく見かけるのが、「シジミ◯◯個分のオルニチン入り!」などと表示されている加工食品です。
味噌汁やスープ類が多くありますが、インスタントラーメンにシジミが入っています。
(オルニチン含有量:単位「シジミ1個あたり0.4mgで換算」)
【キリン・ウコンとしじみ900個分のオルニチン】400mg:100ml入りビン
【マルコメ・貝だし液みそ】68mg:一杯あたり
【日清・香るしじみだし醤油ラーメン】30mg:1個
【トップバリュ・オルニチン入ウコン顆粒】50mg:1袋
【トップバリュ・しじみわかめスープ】37mg:一杯あたり
【ひかり味噌・元気プラスオルニチン入りおみそ汁】37mg:一杯あたり
【永谷園・しじみ70個分のちから】25mg:一杯あたり
【ヒゲタ・しじみ醤油】12mg:大さじ一杯(15ml)
【トーノー・オルニチン入さんぴん水】10mg:100mlあたり
5.オルニチンの1日の目安摂取量と上限摂取量はどのくらい?
【1日の目安摂取量】400mg〜1000mg
【1日の上限摂取量】10g以上
一般的に、オルニチンの1日の目安摂取量は400mg〜1000mg程度といわれています。
シジミに含まれているオルニチンの量は100g中に10.7〜15.3mg 、本しめじでも100g中に160mg程度ですので、オルニチンを多く含む食品(食材)を組み合わせても、普段の食事からの摂取では過剰になることがほとんどありません。
むしろ、食品(食材)から1日のオルニチン目安摂取量を満たす方が難しいです。
オルニチンの上限摂取量は、1日10g以上を摂取した際に、下痢や胃痛といった症状が現れたという報告があります。
1日10g以上を摂取すると下痢や胃痛といった症状から、オルニチンの過剰摂取で重篤な副作用の症状は起こりにくいもの、軽度の消化器官系炎症が引き起こる可能性があります。
6.オルチニンに副作用があるのか?
オルニチンは、そもそも体内で生成される成分であるので、外部からのオルニチンも問題なく体内で役立つとされています。
オルニチン自体に副作用の心配は、基本的にありませんが、過剰摂取による副作用が絶対にないとは言いきれません。
オルニチンは1日10g以上を過剰摂取してしまうと、胃痛や下痢などの症状が現れることがあります。
・胃痛
・下痢
7.安全規格を取得しているサプリメントを選び方
毎日サプリメントを摂取し続けるためにも、安全性がしっかり守られているサプリメントを選ぶことが大切になります。
衛生管理や安全管理がしっかりしていない会社のサプリメントを摂取したくありませんよね。
安全のお墨付きがあるサプリメントを確認するには、3つの安全基準があります。
(1)有機JAS認証
(2)GMP基準
(3)HACCP(ハサップ)
(1)有機JAS認証
有機JASマークは、農薬や化学肥料などの化学物質を使用していないので、自然界の力で生産された食品にのみ付けられます。
有機食品のJAS規格に適合した生産が行われていることを登録認定機関が検査して、認定された事業者のみが有機JASマークを貼ることができます。
(2)GMP基準
医薬品の製造には、適正・製造規範の略で「GMP(Good Manufacturing Practice)」という制度があります。
原材料の受け入れ・製造・出荷のすべての家庭において、製品が「安全」で「一定の品質」が保たれるようにするための製造工程管理基準のことになります。
(3)HACCP(ハサップ)
HACCPとは、食品の中に潜む危害要因を科学的に分析し、危害要因が除去、あるいは安全な範囲まで低減できる工程を常時管理して記録することになります。
継続的に安全確認をおこなう安全管理手法で極めて高い安全性を確保している証になります。
8.オルニチンの疲労回復効果がスゴイ理由!
オルニチンは、疲労回復効果がスゴイ理由は、多くのオルニチンのサプリメントを愛用者の声らからも実感していただけるはずです。
シジミや本しめじなどオルニチンを含んでいる食品(食材)はありますが、疲労回復効果を期待するのであれば、サプリメントを利用する方が手軽で効率的に摂取できます。
サプリメントで効率良くオルニチンを摂取することで、「筋肉質で疲れにくい体作り!」や「朝の目覚めがスッキリしたり」など、体調と体質の変化が期待できます。
9.「オルニチンは疲労回復に効果があるのか?副作用はあるのか?」まとめ
「オルニチンは疲労回復に効果があるのか?副作用はあるのか?」について解説してきました。
最後におさらいとして、「オルニチンは疲労回復に効果があるのか?副作用はあるのか?」に要点をまとめてみます。
■オルニチンが疲労回復効果をもたらす理由とメカニズム
(1)解毒作用が促進されるため!
(2)エネルギー産生が円滑に進むため!
■オルニチンの疲労回復効果の種類
(1)精神的疲労・ストレスの軽減
(2) 疲労臭軽減
(3)二日酔い・アルコール性の疲労軽減
(4)運動による疲労軽減
■オルニチンの疲労回復効果がスゴイ理由!
■オルニチンが多く含まれている食品(食材)
(100g中のオルニチン含有量:オルニチン100g相当の量)
【シジミ】10.7〜15.3mg :約35個
【ヒラメ】0.6〜4.2mg :約1切れ
【キハダマグロ】1.9〜7.2mg:刺身7〜10切れ
【チーズ】0.8〜8.5mg:約5枚(スライスチーズ)
【えのき茸】14.0mg:約1.2袋
■オルニチンの摂取量
【1日の目安摂取量】400mg〜1000mg
【1日の上限摂取量】10g以上
■オルニチン自体に副作用の心配は、基本的にありませんが、過剰摂取による副作用が絶対にないとは言いきれません!
■オルニチンの過剰摂取による副作用の症状
・胃痛
・下痢
■3つの安全基準
(1)有機JAS認証
(2)GMP基準
(3)HACCP(ハサップ)
最後までお読みいただきありがとうございました!