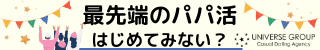このページは、「シトルリンを過剰摂取するとシトルリン血症になるの?シトルリン血症の原因と治療法!」について、わかりやすく解説していきますので、参考にしてもらうためにお伝えしていきます。
シトルリンといえば、男性向けの精力剤や精力増強、女性向けのダイエットや美容などのサプリメントに多く含まれている成分になります。
シトルリンは、天然の栄養素なので、基本的には副作用はありません。
シトルリンを過剰摂取するとシトルリン血症になるリスクがあるのでしょうか?
シトルリン血症とは、どのような病気で、原因と治療法はあるのでしょうか?
では、「シトルリンを過剰摂取するとシトルリン血症になるの?シトルリン血症の原因と治療法!」について詳しく解説していきます。
1.シトルリンを過剰摂取するとシトルリン血症になるの?
体の体内で発生するアンモニアは、尿素回路(オルニチンサイクル)と呼ばれる過程を経て、尿素に変えられます。
『シトルリン→アルギノコハク酸→アルギニン→シトルリン』
シトルリン血症は、尿素サイクル異常症の一つになります。
アルギニノコハク酸合成酵素の活性が、低下しているので、血中にシトルリンが蓄積して、シトルリンが尿中に排出されるようになり、シトルリン血症を発症します。
血液中にアンモニアが増加して、体に悪影響を及ぼします。
原因は、明らかにわかっていないのですが、肝機能の先天的な異常が疑われています。
約50万人に1人の割合で発症して、日本国内には6000人程度の患者しかいない難病になります。
シトルリン血症は、20代以降の男性に多い病気になりますが、シトルリンを多く摂取するとなるという病気ではありません。
サプリメントなどで、シトルリンを摂取しても、シトルリン血症になるというリスクはありません。
シトルリン血症とは、シトルリン処理ができなくて、血中のシトルリン濃度が高くなることであり、シトルリンが体に悪影響を与えているわけではありません。
2.そもそもシトルリン血症とはどんな病気なのか?
シトルリン血症とは、先天性のアミノ酸代謝異常症の病気になります。
血液と尿のシトルリン濃度が異常に高まるために、シトルリン血症といわれています。
シトルリン血症を正確に言うと、「アルギニノコハク酸合成酵素欠損症」と呼ばれています。
アルギノコハク酸という酵素を肝臓が作れずに、血中シトルリン濃度が上昇した状態になります。
アンモニアが体内で代謝されずに、アンモニア中毒に陥ることで起こります。
肝臓が、作り出す酵素によって、アンモニアから変化され、循環することになるアミノ酸が、アルギニノコハク酸合成酵素がないために、血液中のシトルリン濃度が高くなり、尿から排出されます。
アルギノコハク酸がないと、アルギニノコハク酸尿症は約80万人に1人の難病扱いで、先天的なものである可能性が高いといわれています。
先天性の難病になるので、普通の人がシトルリンを摂取して発症する病気ではありません。
3.シトルリン血症の症状には3つの病型がある
シトルリン血症の症状は、現在3つの病型があります。
(1)Ⅰ型シトルリン血症
(2)Ⅱ型シトルリン血症
(3)Ⅲ型シトルリン血症
(1)Ⅰ型シトルリン血症
Ⅰ型シトルリン血症は、生後まもなく呼吸困難や痙攣(けいれん)を起こし、新生児のうちに死亡します。
(2)Ⅱ型シトルリン血症
Ⅱ型シトルリン血症は、生後5〜8ヶ月頃に嘔吐で始まり、異常な興奮や知能障害を起こします。
新生児例は興奮性亢進、嗜眠、哺乳不良、多呼吸、嘔吐などが生後数日以内に出現し、痙攣(けいれん)、後弓反張(こうきゅうはんちょう)、昏睡などが起こります。
(3)Ⅲ型シトルリン血症
Ⅲ型シトルリン血症は、幼児期以降に発症し、知能障害が起こり、意識を失うの発作を起こします。
小児期例では、反復性嘔吐、痙攣(けいれん)などが起こります。
女性成人例においては、妊娠中あるいは分娩後に高アンモニア血症による意識障害で発症することもあるので、十分に注意が必要になります。
主に、自分がどこで何をしているかわからない状態になったり、ぼんやりするといった意識障害、手の震えなどの症状が起こります。
てんかんや精神分裂病、パーキンソン病などとも、しばしば間違われますが、血液中のアンモニアを測定すると高いことと、血液中のシトルリンが高いことから診断されます。
4.シトルリン血症の原因とは?
シトルリン血症の原因は、シトルリンを分解する酵素が、遺伝的に欠損していることが原因になります。
シトルリン血症の発症には、生活習慣やホルモン作用あるいは遺伝素因など、内外環境の原因が考えられています。
アルギニノコハク酸シンテターゼという酵素が欠損していると、シトルリンからアルギノコハク酸への変換が行われずに、血液中にシトルリンが増加して、尿中に排出されるようになります。
また、20代〜40代に発症するものの、幼少時から豆腐などの大豆製品、ピーナッツ、バター、卵、チーズ、牛乳、魚類、肉類などの高たんぱくの食品(食材)を好み、糖質類(ご飯や甘い物など)を嫌うという傾向にある人が起こりやすい病気になります。
5.シトルリン血症の治療方法とは?
成人期においても、治療の継続が必要になります。
低たんぱく質食事療法が基本となります。
高アンモニア発作を繰り返す時には、肝移植も考慮されます。
急性期には、高濃度のブドウ糖(10%以上)、血液浄化療法(持続血液濾過透析:CHDF)などがあります。
6.「シトルリンを過剰摂取するとシトルリン血症になるの?シトルリン血症の原因と治療方法!」まとめ

「シトルリンを過剰摂取するとシトルリン血症になるの?シトルリン血症の原因と治療方法!」について解説してきました。
最後におさらいとして、「シトルリンを過剰摂取するとシトルリン血症になるの?シトルリン血症の原因と治療方法!」に要点をまとめてみます。
■シトルリン血症とは、先天性のアミノ酸代謝異常症の病気です。
■シトルリン血症の症状には3つの病型
(1)Ⅰ型シトルリン血症
(2)Ⅱ型シトルリン血症
(3)Ⅲ型シトルリン血症
■シトルリン血症の原因は、シトルリンを分解する酵素が遺伝的に欠損していること。
■シトルリン血症の治療方法は低たんぱく質食事療法が基本になります。
最後までお読みいただきありがとうございました!